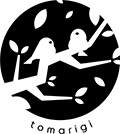200DL記念の後日談SSになります。ヒロイン視点の小説です。
ネタバレを含みますので、ご視聴後の閲覧を推奨します。

午後から降り始めた雨は、世界の埃を洗い流すかのように、しずかにしずかに天から落ちては、柔らかい音を響かせた。
窓を伝って、落ちて弾ける水。しずくの中に映るさかさまの街。夜のように私の姿を隠してくれる厚い雲。私は雨が好きだった。
歩道橋の下で彼を待つ。雑多な夕方の街の音が仕事に疲れた身体に心地いい。スマートフォンを取り出して時間だけ確認すると、私はひんやりとした橋脚に背を預けた。
程なく、革靴が水たまりを踏みつけながら、階段をガンガンと降りてくる不躾な音が耳に届く。こんな野暮な足音を響かせるのは、彼しかいない。
「悪い! 待たせた……。おい、そんな薄着で寒くないか?」
私の服装を見るなり、貴道さんは驚いたような目をした。そんな彼の前髪とカッターシャツだって、雨に濡れてはりついていてとても寒そうなのに。
気安く肩に回されそうになった腕を軽くいなして「平気です」と言うと、彼は少し悲しそうな顔をした。
……その表情に、胃の辺りがじわりと熱くなる。冷えた身体に火種がくすぶる。貴道さんが差した傘に入れてもらうと、私の肩と彼の二の腕が触れ合った。びく、と身体を強張らせる彼。怒られる前の子供のような、痛々しいくらいの緊張が、触れた肩の先に感じられる。私はじっと、その黒い目を見た。
「どうしたんですか」
「いや……二人で入ると、狭いな、と」
「それもそうですね、では私はタクシーで帰りましょう」
「いやいやいや、狭いけど嫌だとは言ってないだろ」
「冗談です」
「お前……あのな、冗談っていうのは受け取る側が面白くならないと冗談にならないだろ」
怒ったように言いながら、それでもほっとしたように、彼の緊張が緩んだのがわかった。
「ところで、今日の晩ごはんですけど何にします?」
「ん? うん? ん〜そうだな、う〜ん……」
貴道さんは首をひねって頭を悩ませる仕草をして、その後通りの飲食店を見回した。雨だからか、少し人通りが少ない。ぽつぽつと、店の先にLEDの灯りが点きはじめる時間だ。
「パスタ、いや……あの店は注文してから持ってくるのが遅い。あっちのフレンチは全部バターの味しかしないし、裏通りの小料理屋は、少しでも残したら嫌な顔されるし……」
私を喜ばせようとしているのか、それともいいところを見せたいのか、色々と考えを巡らせる貴道さんに「そんなに色んなお店に、誰と行ったんですか?」なんて聞きたくなる。
それは、ヤキモチだけの単純なものじゃない。私が妬いていると思って有頂天になる貴道さんの顔を思うと、痛めつけたくなる。喜んで伸びる鼻の下を、足で踏みにじりたい。言葉で、痛みで、性感で、泣かせたくなる。私がこんな気持ちになるのは、貴道さんだけ。私はいつだって、頭の中で彼を打ちのめすシュミュレーションをしている。
「私、居酒屋に行きたいです」
うんうんといつまでも頭を悩ませる貴道さんに業を煮やして、私はすぐそこにある居酒屋を指差した。
「ここチェーンだぞ、あんまり美味くないかもしれない。値段的に若者とか学生も多いし……」
軒下に置かれた雑多なメニュー看板が、雨にうっすら濡れている。貴道さんは困ったように私を見た。
「こんな雨の中、しかも会社帰りでお互い疲れてるのに、美味しいお店を探して歩くほうがめんどくさいです」
それは本当のことだった。安くつく都合のいい女を演じるわけでもなく、ただ単に自分自身、こういったチェーン居酒屋に誰かと入る習慣が今まであまりなかった。
「それに私、貴道さんと色んなものを共有したいので。それが美味しいものでも不味いものでも、なんでも」
私の言葉に、貴道さんはめちゃくちゃ照れたようにまごまごしてから「まあお前がいいって言うなら行こう」と言った。店に入る前に、彼がとても綺麗に傘を畳むのが印象的だった。
私たちが通されたのは、奥の方の間仕切りされた個室だった。貴道さんがドラマみたいにテキパキと、ビールやおつまみを頼むところが見られるかと思ったけれど、最近はどこの店もタッチパネルでの注文のようだ。
「へえ、すごい……お酒、色々ありますね」
「お前が家に置いてるような、良さそうなワインはないぞ」
「あれって良いものなんですか? ワインには疎くて」
キッチンの一角にある、ほぼ使われていないワインセラーを思い出した。父の仕事先の人に引越し祝いに貰ってからずっと、掃除のときも表面の埃をさっと拭くだけの、まるで置物になっている。
「実は私、人前であまりお酒を飲んだことないんです」
大学や会社の飲み会も、ずっと断り続けてきた。ノリの悪い、コミュ障の女だとみんなに思われている事だろう。でも、気を許していない人たちと一緒にお酒を飲んで、もし我を忘れてしまったら。そう思うととても怖かったのだ。
「へえ……人の飲み物にクスリは仕込むのに、変な女だなお前は」
「ふふ、それはごもっともです」
貴道さんは片眉を上げて笑うと、店員さんが持ってきたビールのジョッキをくいっと掲げて口をつけた。彼の喉仏が上下するのを、ジョッキの持ち手に絡む指の骨を見つめる。手の甲の筋から、半袖の腕に伸びる筋肉まで、全て知っているとはいえ、改めてそれらを見ていると喰らいつきたくなってくる。
「おいしそう」
ふと、口をついて出た。
「ん? ああ、たくさん食べてくれていいぞ」
何を勘違いしたのか、貴道さんは焼き鳥の串を差し出してきた。私はそれを受け取ると、半ばやけくそ気味に一気に頬張り、手元のビールで流し込んだ。
「おいおい、そんな一気に……」
舌の根を刺す芳醇な苦味にクラリとする。こんな苦くて不味いものを美味しそうに飲んでいるなんて、貴道さんは私が思うよりずっと大人だ。私なんかよりも色々な経験を重ねて、まっとうに地に足をつけて生きている大人の男性だ。貴道さんは、足腰立たなくなるまで酔っ払わないでくれよ、と笑った。私がこんなに彼に執着するのは、自分への自信のなさの裏返しなのかもしれない。
「あ、そうそう。お前が作ってくれたプログラム、あれめっちゃいいな」
貴道さんは、私の目を見て突然ニヤッと笑った。いたずらっ子みたいな笑顔に、一瞬怯んでしまう。
「ああ……、ゾウリムシでも一目でわかる部署のタスク管理システムですか」
「そのひどい名前は要検討だけどな。でも俺が現場にいない時に、誰の手が空きそうとか、ぱっとわかるのは有り難いんだよ」
熱っぽく語るその口ぶりに、彼の仕事に対する真剣さが伺える。そこらへんのシステムの雛形を使って、貴道さんでも見やすいように少しいじっただけなのに。熱意を持って取り組めるまともな物事があることに、少し嫉妬する。それと同時に、この一見まともそうな男が、夜になると自分に女のように足を開いて跪いている異常さを思うとたまらない。
「できる女ですから」
私はビールを一口飲み、タッチパネルのメニューに目を向ける。暗い外からゴロゴロと、猫の喉の音のようなくぐもった遠雷が聞こえた。
貴道さんを見ていると、様々な気持ちが溢れてきて、とても疲弊してしまう。くすぐったいような、泣きたいような。でも触れようとしたら消えてしまいそうな。だから、私はつい彼の本質から目を背けてしまう。
貴道さんは、こんな関係になる前からずっと、気になる存在だった。
気になるとは言っても好きとかじゃなく、むしろ気にくわないから、やることなすこと目についてはカンに障る、くらいの勢いだった。その点では私たちは、お互いに意識し合っていたことになる。
あの夜、本当に上なのはどっちなのかわからせるつもりだったのに。いつの間にかこんなに彼を愛おしく思うようになるなんて、全く計算外だった。
「どうした? なんか疲れてるのか?」
そう言った彼の手が、心配そうに私の額に触れ……
「いたたたたた!」
る前に手首を掴んで逆方向に捻り上げる。テーブルを挟んで、貴道さんは関節を拗じられる痛みにしばし悶絶した。
「大丈夫です。低気圧に弱くて、私」
「嘘だろ、めっちゃ強いじゃねえか……」
貴道さんの、女に触れることを躊躇わないところが信じられない。自分は女に触れても嫌がられないという自信の裏付けみたいに、ごく自然に手が動くのが腹立たしかったし、何より今までの女と一緒にしてほしくなかった。これは小さな反抗のつもりなのだ。
私たちが店を出る頃には、あれだけ荒れていた夕空が、すっかり雲を彼方に追いやっていた。湿った空気と、飲食店の換気扇から漏れる焼き物の匂いが混ざったものが、ぬるく鼻腔を撫でていく。
「ふふ、ごちそうさまでした、お腹いっぱいです。貴道さんが美味しくないなんて言うから、どんなものかと思ってましたけど……悪くなかったです」
「俺は、美味くない『かも』って言ったんだ」
ほんのりと朱くなった彼の頸からうっすら立ち上る、かすかな汗とアルコールの匂い。胸の内側にきつく爪を立てるようなきゅんとした劣情に、思わず頬が弛む。
「何をニヤけてるんだ」
私は手を差し出した。
「少し酔っ払ってしまったようなので、お願いします」
「何を……?」
「エスコートです」
彼の手をおもむろにギュッと握った。男性にしてはしっとりとしていて、思いの外柔らかい掌だ。貴道さんは目をまんまるにして驚いているふうだったが、そのままゆるく握り返すと、ぎこちなく歩き始めた。
「不思議ですね、私たち。大人なのに手を繋ぐの、これがはじめて。あんなこともそんなこともして、処女まで喪失したのに。貴道さんが」
「おまっ……やめろ、酔っぱらい。こんな往来でなんてこと言うんだ」
本当は酔っ払ってなんていない。でも、都合がいいからお酒のせいにしよう。
「貴道さん、私、憧れていたことがあるんです」
「なんだ? シメの牛丼でも食べたいか?」
「違います、はしご酒ってやつです」
帰りたくなかった。今なら自分から、貴道さんに少しでも触れられる気がしていた。
普通の恋人みたいな愛し方はできないかもしれないけど、それでも私にだって、少しは歩み寄りたいという気持ちもある。それは確かな気持ちだ。
「俺は明日も仕事なんだが?」
そう言いながらも嬉しそうな彼の横顔を見上げる。雨上がりの蒸気が夜の街の灯りをじわりと滲ませて、柔らかく彼の頬がを照らしていた。